
こんにちわ、ゆたかです。
今日は『夢を叶えるゾウ0』を読んでいきます。

『夢を叶えるゾウ』といえば、シリーズ化もされている人気の自己啓発本よね。今回のお話はどんな内容なの?

今回は、夢を持たずに毎日をなんとなく過ごしている、平凡な会社員が主人公。課長からのパワハラにも耐えながら、ただ時間をやり過ごしていたんだ。

そこに、またあのガネーシャが登場するのね!

そう。主人公はガネーシャから次々と課題を出されて、それをクリアする中で「本物の夢」を見つけていくことになるんだ。

本物の夢かぁ……。どんなものなのかな?

興味が湧いてきたところで、さっそく物語を見ていこう!
第1章:夢を持たない僕にガネーシャが教えてくれたこと
平凡な会社員である主人公は、毎日をただこなすように過ごしていた。課長からのパワハラにも耐え、心のどこかで「こんなものか」と諦めていた。夢も希望も持たず、ただ目の前の業務を処理するだけの毎日。しかしある日、象の神様・ガネーシャが突如現れ、主人公の生活は大きく変わっていく。「夢がないのはダメじゃない。でも、夢は自分の人生のエネルギーや」とガネーシャは言う。最初に与えられた課題は、「朝日を浴びる」「好きなものを見つける」。日々のなかで自分が気持ちよく感じる瞬間、惹かれる匂いや人、物に気づくことで、心の奥にある本音に耳を傾ける訓練だった。主人公は幼い頃、おばあちゃんと一緒に食べたもんじゃ焼きの思い出に辿り着く。しかし、それは周囲の「服に匂いがつく」「油っぽい」という意見で遠ざけていたものだった。他人の目を優先することが習慣になり、自分の「好き」を抑えてきたことに初めて気づいた。「夢を持つ」とは、特別な才能や目標を持つことではなく、自分の内側にある静かな声を丁寧に拾い上げることなのだ。その第一歩として、主人公の「再発見」が始まった。

夢には、自分の「好きだったこと」や「心地よいと感じる瞬間」を知ることが大事なんだね。

そうだね。日々をなんとなく過ごしていると、つい「やりたいこと」より「やるべきこと」に偏ってしまう。だからこそ、「自分の本音」に向き合う作業って、すごく大切なんだ。

夢の最初の一歩は、「誰かに自慢できるような大きな目標」じゃなくて、自分の内側にある“ほんの小さな好奇心”に気づくことだったんだね。次は、どんな課題が出されるのかな?

それじゃあ、さっそく次の課題を見ていこう!
第2章:初めての体験が、自分の感情を目覚めさせる
ガネーシャから与えられる課題は、どれも一見すると単純で意味がないように思えるものばかりだ。しかし、実行してみると、不思議と心が動き出す。今回の課題は「初めてのことをする」「競馬に行って、こんなことが起きたら面白いと想像してみる」など、日常の外へと踏み出す内容だった。主人公は戸惑いながらも、競馬場で「もしこの馬が勝ったらすごいな」と想像する。それが現実になるかどうかより、「ワクワクすることを考える」という感覚そのものが新鮮だった。そこに、“楽しい”の本質がある。最高の楽しいとは、経験したことのないことに対して想像を働かせ、実際に行動してみることで見えてくるのだと気づく。さらに、日常に「初めて」を増やすよう意識してみると、自分の中にある感情の動きが少しずつはっきりしてくる。良い感情だけでなく、不安や恐れも観察するようになる。例えば、森の中でスマホを使わずに過ごしてみる。何もない時間に浮かぶのは、自分の本音や忘れていた記憶。自然の音に耳を澄ませ、目の前の世界を味わううちに、心が整っていくのを感じる。インターネットという便利な刺激を断ち、ゆっくりとした時間を取り戻すことで、短期的な欲求(スマホを見る、寝る、怠ける)と、長期的な欲求(成長したい、何かを成し遂げたい)の違いがわかってくる。夢は空から降ってくるものではない。感情に目を向け、新しい体験を積み重ねていくことで、自然と姿を現してくる。主人公の中で、「自分は何をしているとき、心が動くのか?」という問いが生まれ始めていた。

想像するって、思った以上に心が動くんだね。

うん。やってみるまでは「意味あるのかな?」って思うけど、実際に体験すると感情が反応するのが分かるよね。

でも、ガネーシャの課題って、なんでこんなに“シンプルだけど深い”んだろう?

たぶん、自分の感情とちゃんと向き合えるように、少しずつ準備させてくれてるんだと思うよ。次の課題では、いよいよ“自分の内面”をもっと深く見つめることになるんだ。

えっ、もっと深くって……どういうこと?

次はね、「やりたくないこと」に向き合うんだって。

うわ、それはちょっとキツそう……。

でもそこに、“本当にやりたいこと”のヒントが隠れてるんだよ。さっそく、その続きも読んでみよう!
第3章:やりたくないことが、やりたいことを教えてくれる
次の課題は、「やりたくないことを全部書き出す」ことだった。主人公は真っ先に「会社に行きたくない」と書く。けれど、ガネーシャはその言葉の裏側を深掘りさせる。「ほんまに、それ全部が嫌なんか?」と。振り返ると、仕事そのものが嫌なわけではない。人間関係の悪さや、理不尽な上司とのやり取りに心を消耗していたのだ。では、どういう働き方なら続けたいと思えるのか? そこで出てきたのが、「尊敬できる仲間と夢中になって働きたい」という願いだった。「やりたくないこと」は、実は「やりたいこと」へのヒントになる。反対の言葉に置き換えてみれば、自分の望む環境や価値観が見えてくる。また、自分の怒りや苦しみと向き合うことも、夢の一部だと教えられる。怒りを感じたとき、相手に伝えるのは「自分を大切にする」という行為。苦手な人には、その人なりの信念がある。それを理解しようとすることで、共感力が広がる。これは、人と共に何かを成し遂げるうえで、欠かせない力でもある。さらに、主人公はリモート交流会や職業体験に参加し、自分と異なるバックグラウンドを持つ人々と接していく。そのなかで、「こういう仕事、意外と面白そうだな」「この人たちとなら頑張れそうだな」といった感覚を得る。自分に合った働き方とは、自分の価値観と合う人との出会いから生まれる。やりたいことが、少しずつ形を持ち始めていた。

へぇ……「やりたくないこと」から「やりたいこと」が見えてくるなんて、思ってもみなかった。

ネガティブな感情って、ただの不満じゃなくて、“本音のヒント”でもあるんだね。

自分が何に怒ってるのか、何をつらいと感じてるのかって、ふだんあんまり深く考えないかも。

そうそう。でも、ちゃんと向き合うと、「本当はどうしたいのか」が少しずつ見えてくる。

……でも、夢って、好きなこととか、やりたいことでできてるだけじゃない気もするんだよね。

うん。ガネーシャも言ってたけど、夢の最後のカギになるのは――「痛み」との向き合い方なんだって。

痛み……か。それって、どういうことなんだろう?

気になるよね。それじゃあ次は、ガネーシャが教えてくれる「本物の夢」の形を見ていこう。
第4章:痛みが教えてくれる、本物の夢のかたち
夢を見つけるうえで最後に必要なのは、「痛み」と向き合うことだった。ガネーシャはこう言う。「夢は、自分を救うことで終わったらあかん。他人も救おうとしたとき、ほんまの夢になるんや」。主人公は、自分が抱えてきた心の痛み――理不尽な上司からの暴言、誰にも頼れなかった孤独、無力さ――に目を向ける。それは決して美しいものではない。けれど、その痛みから生まれた感情こそが、彼の原動力になっていた。「傷つけられないだけの力を持ちたい」「誰かに認められたい」――そんな願いを、彼は自分のなかでずっと否定してきた。けれど今、その想いを受け入れられるようになった。夢は、必ずしも高尚で美しいものじゃない。むしろ、泥臭くて、悔しくて、切実な願いから生まれることがある。そして、同じような痛みを抱えている誰かを助けたいと思ったとき、その夢は自分のためだけでなく、社会や人のために拡張される。それは「エゴ」ではなく、「共感による拡張」なのだ。ガネーシャは言う。「誰かのことを、まるごと愛せるようになったら、自分のことも好きになれるで」。主人公は今、完璧じゃない自分、情けない過去もすべて受け入れて、新しい一歩を踏み出そうとしていた。夢とは、“こうなりたい”ではなく、“こうありたい”という願い。そしてその願いは、過去の痛みとしっかり向き合ったときに、ようやく「本物」になるのだと知った。

そうか……夢って、キラキラした理想だけじゃなくて、過去の痛みや悔しさともちゃんと向き合うことが大切なんだね。

うん。むしろ、そこにこそ「本物の夢」の芽が隠れてるのかもしれない。

たしかに、自分が一番つらかった経験って、誰かの役に立てるきっかけになることもあるよね。

そうだね。それに気づいたとき、夢は「自分を救うもの」から「誰かを救うもの」へと変わっていくんだと思う。

……なんか、今まで思ってた“夢”とは、ずいぶん違うものだったなぁ。

うん。だからこそ、この本を読んで得た気づきを、ちゃんと振り返っておきたいよね。

それじゃあ最後に、『夢を叶えるゾウ0』からの学びと成長をまとめてみよう。
学びと成長
『夢を叶えるゾウ0』を読んで、感じたこと。それは夢って、特別な才能や立派な目標がある人だけのものではないということです。ガネーシャが主人公に出す課題は、「朝日を浴びる」「好きなものを見つける」「やりたくないことを書く」といった、ごく普通の行動。でも、それを丁寧にやることで、自分の心の声に気づけるようになる。僕もふだん、自分の感情にフタをして、「なんとなく」で毎日を流していた気がします。けれど、夢の正体って、「こうなりたい」より「こうありたい」という、もっと切実で、もっと人間らしい願いなのかもしれません。傷ついた経験も、抱えた孤独も、ちゃんと見つめれば夢の原動力になり得る。この本は、「弱さがあるからこそ、誰かを救いたいと思える」と教えてくれました。自分と向き合うのは怖い。でも、その先にしか、本物の夢も、本物の成長もないんだと心から感じた一冊でした。
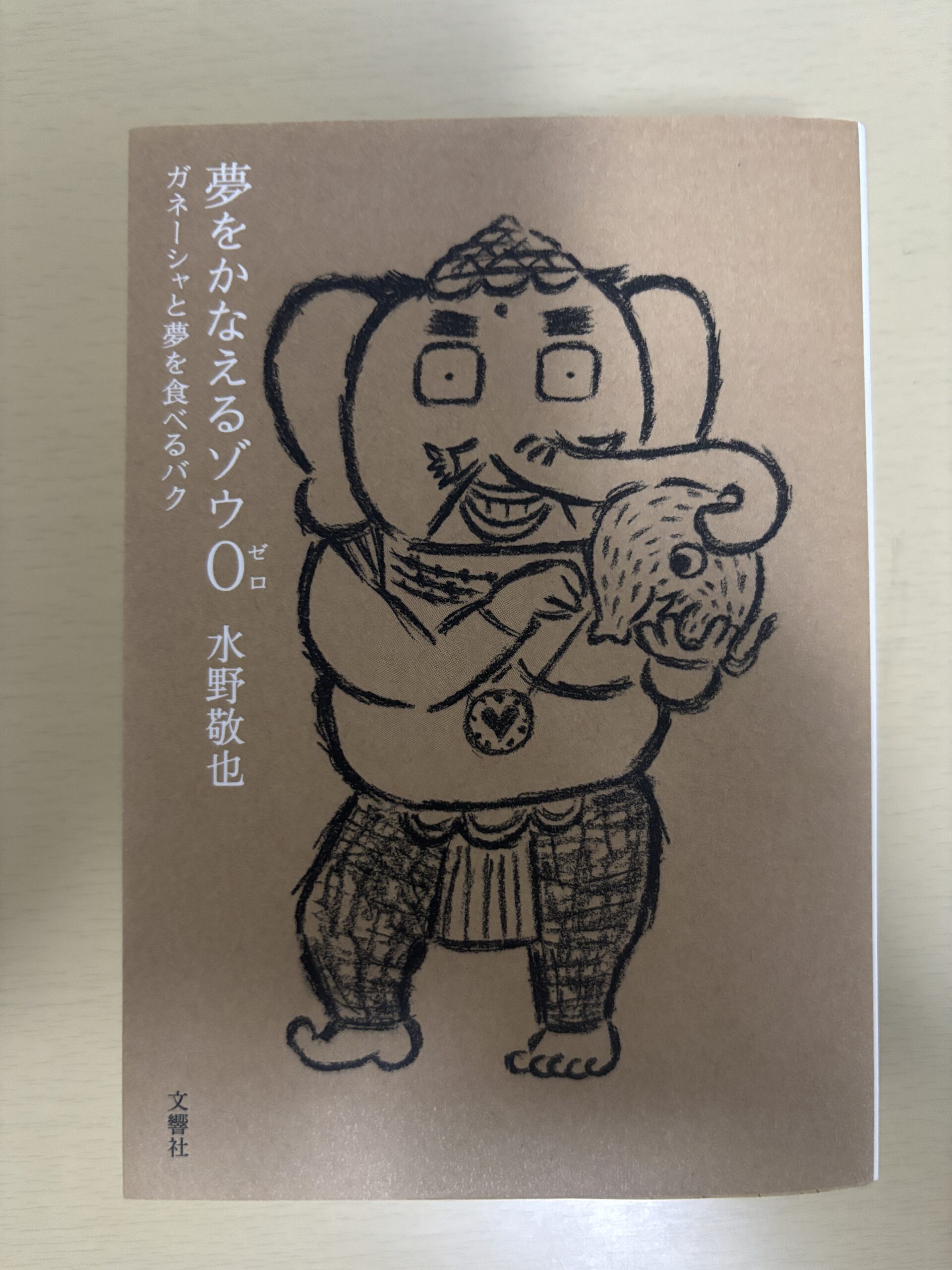

コメント